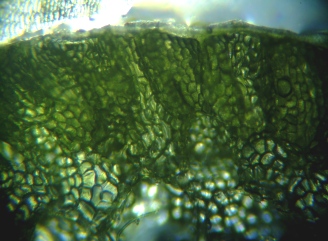�m�����ԍ��F�O�P�P�W�n
�y�͂��߂� INTRODUCTION�z
�ۍj�E�[�j�S�P�ځE�E�L�S�P�� �C�`���E�E�L�S�P Ricciocarpos natans (L.) Corda �́A
���č����̐��c���ɕ��ʂɌ������d�ۗނ́A�ЂƂł������B
�������A�ߔN�̓y�n�J�����ƁE�p���H�̒������E�O�ʃR���N���[�g���蓙�̊����ρA�_��A�����������ɂ��A
���R���z��͋}���ɋ��܂�A���ɂ͊��Ȃ́A���b�h�f�[�^�u�b�N��
�u�d�ۗ� �b�q�{�d�m(��Ŋ뜜�T��) �v�ƋL�ڂ����Ɏ������i���O�P���R���ǐ������l���Z���^�[�E�������l�����V�X�e���j�B
�����ŁA����͐�t���ɂ����Đg�߂ȟ��p���ߒr�ł���A�����s���ݗY�փP�r�i���O�Q�j��
��ɂƂ�A���Ƃɗ��炸�A��ʎs�����x�������{�\�Ȏ�@��p���āA
�C�`���E�E�L�S�P�̌����ʂ𖾂炩�ɂ��邽�߂̒��������{�����B
�C�`���E�E�L�S�P�̑S�i�i���Ձj�Ɛ����p���i�p�j��Fig.01-02�ɁA�t��́i�㕔�j���f�ʂƉ����̐�[����Fig.01b-02b�Ɏ����B
 
fig.01 �X�|���W��̗t��� fig.02 �ؕЂ�������������
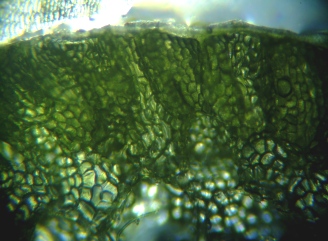 
fig.01b �t��́i�㕔�j���f�ʁi�������ʐ^�j fig.02b �����̐�[���i�������ʐ^�j
��
�y�ޗ��y�ѕ��@�@MATERIALS AND METHDS�z
�Y�փP�r�̐��ӂ�k���Œ������A�C�`���E�E�L�S�P�̌������m�F�����G���A�R�P���̓��A
�Q�P����I�����A�R�h���[�g�@�ɂ�钲���g�����ꂼ��P���ݒu�����B
�P���̖ʐς́A�e�X�T�O�����~�T�O�����i�O�D�Q�T���Q�j�Ƃ��A�g�̎x���W�{�͗Y�փP�r
���V�U�����e�Ɋ������̂Ă��Ă����͂ꂽ�|���g�p�����B
�g�́A�z�[���Z���^�[���Ŏs�̂���Ă���|���v���s����������q���i�F�j���A
��ӂT�O�����ƂȂ�悤�������g�p�����B
��������́A�s�̂̃R���x�b�N�X�i�T�D�T�����̋y�тQ�O�����́j���g�p�����B
�P���ist.k01�j�͋����̑������C�`���E�E�L�S�P�ɔ���Ă���ꏊ�Ƃ��A
�ʂ̂P���ist.m01�j�͋����̑S���ɃC�`���E�E�L�S�P�����W���Ă���ꏊ�ɐݒu�����B
���v�Q�����f�W�^���J�����̐������掿���[�h�Ŏʐ^�B�e����Ƌ��ɁA�G���A�R�P�����̊e�������Ƃɖڎ��ɂ��A
�����C�`���E�E�L�S�P�ʂ̑e�����u�܂�E�����E�S�ʖ��W�v�̂R�i�K�Ɏ��ʂ��A
�i�K���Ƃ̖ʐς𑪒肵�A�L�^�����B
�A���A�������掿�f�W�^���ʐ^���p�\�R���Ɉڂ��A�p�\�R���̃f�B�X�v���[�i�Q�P�C���`�j��ŁA
�X�N���[�������Ȃ���A���ist.k01-st.m01�j���̃C�`���E�E�L�S�P�S�����𐔂��i���̑召�͕s��Ƃ����j�A
�u�����̑������C�`���E�E�L�S�P�ɔ���Ă���ꏊ�v�y��
�u�����̑S���ɃC�`���E�E�L�S�P�����W���Ă���ꏊ�v�̑S���������l���擾�����B
�����C�`���E�E�L�S�P�ʂ̑e���i�K�ʂɁA�u�S�ʖ����������l���P�D�O�v�E�u�����������l���P�D�O�v�E
�u�܂灁�����̔������O�D�T�v�̌W����^���A�S���������l�ɌW���Ɩʐς��悶�A�ʐς��Ƃ̑S�����Ɋ��Z�E���肵���B
��
�y���ʁ@RESULTS�z
�Q�O�O�W�N�O�R���Q�U���i���j�E�P�O�F�R�O�`�P�R�F�R�O�E�V�V�E�����j�ɐݒu�����A�P���ist.k01�j�y��
�ʂ̂P���ist.m01�j���AFig.03-04�Ɏ����B
 
fig.03 �ist.k01�j fig.04 �ist.m01�j
���ist.k01�j�́u�����̑������C�`���E�E�L�S�P�ɔ���Ă���ꏊ�v�ŁA
���ist.m01�j�́u�����̑S���ɃC�`���E�E�L�S�P�����W���Ă���ꏊ�v�Ƃ����B
�܂��A�ist.mn�j�ɂ́A�����g�͐ݒu���Ă��Ȃ����A�ist.k01�j�y�сist.m01�j�Ɠ��l�ɁA
�����C�`���E�E�L�S�P�ʂ̑e�����A�R�i�K�Ɏ��ʂ��A�i�K���Ƃ̖ʐς𑪒肵�A�L�^�����B
�G���A�R�P���ɂ��āA�i�K���Ƃ̖ʐρE�S���������l�E�S��������l�����ATable.01�Ɏ����B
| �G���A |
�������� |
�Z�o�ʐ� |
�e����� |
�W�� |
���� |
�S���� |
���̑� |
�@ |
�@ |
| st.k01 |
�O�D�T�~�O�D�T�� |
0.25 |
���� |
- |
1230 |
1230 |
���[�O�`�Q�O�����E���F���� |
| k02 |
�P�D�T�~�T�D�O�� |
7.5 |
���� |
1 |
�@ |
36900 |
����E���������|�̒� |
| k03 |
�P�D�T�~�T�D�O�� |
7.5 |
���� |
1 |
�@ |
36900 |
���[�O�`�Q�O�����E���F���� |
| k04 |
�T�D�O�~�Q�D�O�� |
10 |
�܂� |
0.5 |
�@ |
24600 |
���� |
�@ |
�@ |
| k05 |
�T�D�O�~�T�D�O�� |
25 |
���� |
1 |
�@ |
123000 |
���� |
�@ |
�@ |
| �v |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
222630 |
�@ |
�@ |
�@ |
| �G���A |
�������� |
�Z�o�ʐ� |
�e����� |
�W�� |
���� |
�S���� |
���̑� |
�@ |
�@ |
| st.m01 |
�O�D�T�~�O�D�T�� |
0.25 |
�S�ʖ��W |
- |
8000 |
8000 |
���[�O�`�Q�O�����E���F���� |
| m02 |
�P�D�O�~�T�D�O�� |
5 |
�S�ʖ��W |
1 |
�@ |
160000 |
���� |
�@ |
�@ |
| m03 |
�Q�D�O�~�P�T�D�O�� |
30 |
�S�ʖ��W |
1 |
�@ |
960000 |
���� |
�@ |
�@ |
| m04 |
�P�D�O�~�S�O�D�O�� |
40 |
�܂� |
0.5 |
�@ |
98400 |
���� |
�@ |
�@ |
| �v |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
1226400 |
�@ |
�@ |
�@ |
| �G���A |
�������� |
�Z�o�ʐ� |
�e����� |
�W�� |
���� |
�S���� |
���̑� |
�@ |
�@ |
| mn01 |
�Q�O�D�O�~�R�D�O�� |
60 |
�܂� |
0.5 |
�@ |
147600 |
���[�O�`�P�O�����E���F���� |
| mn02 |
�P�D�O�~�P�O�D�O�� |
10 |
�S�ʖ��W |
1 |
�@ |
320000 |
���� |
�@ |
�@ |
| mn03 |
�T�D�O�~�P�O�D�O�� |
50 |
�S�ʖ��W |
1 |
�@ |
1600000 |
����E�͂ꃈ�V���̒� |
�@ |
| �v |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
2067600 |
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ���v |
�@ |
245.5 |
�@ |
�@ |
�@ |
3516630 |
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Table.01 �Y�փP�r�R�G���A�̃C�`���E�E�L�S�P�����l�y�ёS��������l
�Y�փP�r�Ɍ�������C�`���E�E�L�S�P�́A�R�G���A�̍��v�Q�S�T�D�T���Q�ɕ��z���m�F�����B
�J�E���g���������l��p�����S��������l�́A�R�C�T�P�U�C�U�R�O���ł��邱�Ƃ��A���炩�ɂȂ����B
��
�y�l�@�@DISCUSSION�z
�����R�ی�s���̊ϓ_����
�C�`���E�E�L�S�P�́A���Ȃ̃��b�h�f�[�^�u�b�N�Łu�d�ۗ� �b�q�{�d�m(��Ŋ뜜�T��) �v�Ƃ����B
�P�X�X�X�N�̐�t�����b�h�f�[�^�u�b�N�i�A���ҁj�ł́u�d�ۗ�,�`�@�ŏd�v�ی쐶���v�ł������i���O�R�j�B
�������A�Q�O�O�S�N�̐�t�����b�h���X�g�Łu�a�|�c �ی��v���鐶���v�Ɋi�������ꂽ�i���O�S�j�B
���ꂼ��̃J�e�S���[��Δ䂵�A���̒�`���ATable.02�Ɏ����B
| �@ |
���� |
��t�����b�h�f�[�^�u�b�N�i�A���ҁj
�P�X�X�X�N |
��t�����b�h���X�g
�Q�O�O�S�N |
| �J�e�S���[ |
�d�ۗ�
�b�q�{�d�m
��Ŋ뜜�T�� |
�d�ۗ�
�`
�ŏd�v�ی쐶�� |
�d�ۗ�
�a�|�c
�ی��v���鐶�� |
| ���̒�` |
��ł̊�@��
�m������� |
�̐����ɂ߂ď��Ȃ��A�����E��������ɂ߂Č����Ă���A
�����E����n�̂قƂ�ǂ������ς̊�@�ɂ���A�Ȃǂ̏�
���鐶���B���u����߁X�ɂ���t�������ŁA���邢�͂����
�߂���ԂɂȂ邨���ꂪ������́B
���̃J�e�S���[�ɊY�������̌̐�������������e���y�їv����
�ő���̓w�͂������Čy���܂��͔r������K�v������B |
�a �d�v�ی쐶��
�b �v�ی쐶��
�c ��ʕی쐶��
�a�|�c �ی��v���鐶��
�ۊǑ��ȊO�̐A���ł́A�J�e�S���[�敪�a,�b,�c����ʂ��Ȃ�����
|
Table.02 ���ȁE��t�����b�h�f�[�^�u�b�N�E��t�����b�h���X�g�ɂ�����C�`���E�E�L�S�P�̈���
�C�`���E�E�L�S�P�̈����ɂ��āA���ȂƂP�X�X�X�N�̐�t���͂قړ�������ł������B
�������A�Q�O�O�S�N�̐�t�����b�h���X�g�ł́A���炩�Ƀg�[���_�E�����Ă��邱�Ƃ��C������ł���B
��
�����j�͌J��Ԃ�
�Y�փP�r�ɂ����鐅���A���т̌�����Ԃ́A�P�X�V�W�N����P�X�W�O�N�ɂ����Ă��������A����i�P�X�W�S�j���ڍׂ���Ă���i���O�T�E�p���j�B
�Y�փP�r�̐����A���́A�P�X�V�X�N�O�T���O�V���O�X���ɂقڑS�ʓI�ɐ��ʂ��Ă���A���̊T���͓������Ƀq�Vtrapa�A�������Ƀn�Xnelumbo�A�ł������i���O�T Fig.11�j�B
�������A�P�X�W�O�N�O�T���͒���������ɖ�V�O�����������A�O�X���͂���Ɋg�債��W�O�������ł��Ă���i���O�T Fig.11�j�B
���̌���������i�P�X�W�S�j�́A
�uthe considerable reduction of surface cover in 1980 occurred as a result of winter drawdown and unfavorable summer weather occurred at that time and/or the introduction of the grass carps.�v�Əq�ׂĂ���B
�v��A�u�i���ʂ��Ă��������A���́j�P�X�W�O�N�̏k���́A�~�G�i�P�X�W�O�N�O�P�`�O�Q���j�������E���ʒቺ�̌��ʋy�сA�D�܂�����ʉĂ̓V��ɉ����āi�܂��́j�����̓����ɂ��N�������v�ƂȂ낤�B
�T�d�ȕ\�����_�ȕ\���ɕύX���A�Z�������Ɍ������Ƃ��������Ȃ�u�\�E�M����������A�����A���т̖�W�O�����P�N�ŏ��ł������v
���Ƃɑ��Ȃ�Ȃ��B
��
���Ăё��H���\�E�M���̕����Ɛ�Ŋ뜜�U�ރK�K�u�^�̌���
�Y�փP�r�ł́A�Q�O�O�U�N�O�Q���ɑ��̔ɖΖh�~��ړI�ɁA�ĂсA���H���\�E�M���i���O�U�E�O�V�E�O�W�j���������ꂽ�B
�Q�O�O�V�N�t�G�E�ċG�E�H�G�܂łɁA�\�E�M�������ȑO�ɔɖ��Ă����A�}�c���E�I�I�J�i�_���E�q�V�E�K�K�u�^�E��
�̒����A���сE���t�A���т̐����A������ŁE������ԂɂȂ�A����ɒ����A���т̃}�R���E���V���̐V����H�Q����Ă���i���O�X�j�B
�����A���т̌�����ԂɂƂ��Ȃ��A��D�̊��グ�ɂ��h�{���̍ėn�o�ɋN�������A���v�����N�g���i�����ށj�̑�ɐB
�����O�����B
���t�A���ł́A���Ȃ̃��b�h�f�[�^�u�b�N�Łu��Ŋ뜜�U�ށE�u�t�v�Ƃ���A
�Q�O�O�S�N�̐�t�����b�h���X�g�Łu�b �v�ی쐶���v�Ɏw�肳�ꂽ�K�K�u�^���A�Y�փP�r�ɂ����Ċ��Ɍ�����Ԃɂ���B
�����A���ю��̗��j�͌J��Ԃ����A�Ăѓ��������s������B
��̍���i�P�X�W�S�j�̂P�X�W�O�N�����̗l�����A�Q�O�O�V�N�̗Y�փP�r�ɐS�Ȃ炸���Č�����Ă���B
�\�E�M�������ȑO�̂Q�O�O�R�N�O�X���Q�T���y�у\�E�M��������̂Q�O�O�W�N�O�R���Q�U���́A�K�K�u�^�����|�C���g�̕ω����AFig.05-06�Ɏ����B
 
fig.05 �K�K�u�^�Q���i�Q�O�O�R�N�O�X���Q�T���j fig.06 �K�K�u�^�͌�����ԁi�Q�O�O�W�N�O�R���Q�U���j
��
���Y�փP�r�̖����Ɍ�����
�P�X�W�O�N�̎���E�K�K�u�^�̎���E�y�т����̊܈ӂ���A
�C�`���E�E�L�S�P�ɑ���\�E�M���̐H�Q���뜜�����Ƃ����A�V���ȓ��L����Y�փP�r�ɐ������B
��q���������܂��A��t���́A�M�d�퐅���A���̌p���I���ЂƂȂ蓾��l�דI�����r���̎w�������ׂ��ł͂Ȃ��낤���B
�x���Ɏ��������͔ۂ߂Ȃ����̂́A�p���I���Ђ�f����A�e���x��ቺ�����邱�Ƃ́A�L�ӂł��낤�B
�{�����ł́A�Y�փP�r�̈ꕔ�Ί݂̒T�������{�������A�S�Ί݂ɂ����錻���C�`���E�E�L�S�P�̒T�����͂��߁A���̐�Ŋ뜜��
�̒T���́A���㌟������K�v�����낤�B
��
�y�ӎ��@ACKNOWLEDGMENTS�z
�{���������{����ɓ�����A�Y�փP�r�ɂ�����C�`���E�E�L�S�P�����̏������A�z�[���y�[�W�u�Y�փP�r�o�X�t�B�b�V���O�K�C�h�v�i���O�X�j
��Ɏ҂����[�i�n���h���l�[���j����ɁA�����\���グ��B
�܂��A�_�ސ쌧���Y�Z�p�Z���^�[�����ʎ����ꗘ�g�V�����ɂ͕����{���̗��ւ�^���Ē����A�S��芴�ӂ��܂��B
��
�y�Q�l�����@REFERENCES�z
�i���O�P�j���ȁi�Q�O�O�W�j�F���Ȏ��R���ǐ������l���Z���^�[
�i���O�Q�j�u�U�E���C�N�`�����v�v�u�V�[�N���b�g�E�|�C���g�O�O�O�P�Y�փP�r�v
�i���O�R�j��t���i�P�X�X�X�j�F��t�����b�h�f�[�^�u�b�N�i�A���ҁj�C
�i���O�S�j��t���i�Q�O�O�S�j�F��t�����b�h���X�g�C
�i���O�T�jHidenobu KuNiI�i1984�j�FSeasonal Changes in Water Quality and Surface Cover of Aquatic Plants in Pond Ojaga-ike, Chiba, 1978-1980.
Memoirs of The Faculty of Science, Shimane University, 18, pp.59-68,
�b��a��F����G�L�i�P�X�W�S�j�F�P�X�V�W�N����P�X�W�O�N�ɂ������t���Y�փP�r�̐����ƐA��̋G�ߕω��D������w���w���I�v�i�P�W�j�����D�U�V�D
�i���O�U�j�y���@���E������Y�E�D��`�Y�E�����r�Y�E���q�P�F�i�P�X�V�O�j�F�����E�A���D�����E�P�����D�Ώ��[�C�����C�����D�P�P�|�W�X�D
�i���O�V�j���@��g�i�P�X�W�R�j�F�����D������p�����u�D�V�ÉȊw�Z�p�o�ŎЁC�V�ÁE�����C�����D�Q�O�R�|�Q�O�T�D�i���͏\�Ƀ\�E�����̗��e�Ƀn�l�_�j
�i���O�W�j���c�M��i�P�X�W�U�j�F�\�E�M���W�����������D���Y�����C�搅�Y�����������������D�O�P�|�V�U�D
�i���O�X�j�u�Y�փP�r�o�X�t�B�b�V���O�K�C�h�v
�i���P�O�j��ꖖ�j�E�Όˁ@���i�P�X�W�O�j�F�C�`���E�E�L�S�P�D���{�����A���}�ӁD�k���فC�����C�����D�Q�V�W�|�Q�V�X�D
|