[整理番号:0099]
「明るい釣りの未来を実現するべく、その未来像と道筋について」、
釣りにまつわる様々な問題を、「釣りを楽しむ人々」が中心になって考え、議論し煮詰めてゆく公開の場として、
東京海洋大学水口憲哉名誉教授・同、工藤貴史先生主唱の「釣り問題研究会」が開催されている。
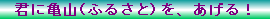 「釣り問題研究会」は開かれたアカデミックな議論の場として、現状認識・問題提起・今後解決
すべき課題の提示等を通じて、釣り人・釣り関係団体・釣り関係メディア・釣り関連産業他への
影響力を持つものと、よしさんは予想し期待している。
「釣り問題研究会」は開かれたアカデミックな議論の場として、現状認識・問題提起・今後解決
すべき課題の提示等を通じて、釣り人・釣り関係団体・釣り関係メディア・釣り関連産業他への
影響力を持つものと、よしさんは予想し期待している。
例えば、漁業経済学会が主催、水産庁の協賛する2005年新規事業「遊漁施策等に関する研究会」(公開)である。
「遊漁施策等に関する研究会」は、
「遊漁に関する実態の把握と情報交換を行うとともに、今後の遊漁に関する施策のあり方等を議論する」
ため「我が国における遊漁の現状と課題」他につき、今年度内に4回程度開催の予定で、
その場でも「釣り問題研究会」での現状認識・問題提起・今後解決すべき課題が継承され、検討される可能性がある。
「遊漁施策等に関する研究会」の成果は、政府へ報告され今後の遊漁に関する施策の参考となされる見込みだ。
単純にいうと「釣り問題研究会」は、「遊漁施策等に関する研究会」を経由し国の施策へ通じる道と位置づけてよかろう。
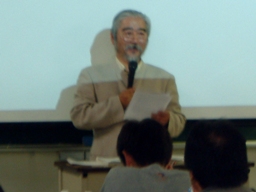
 第1回釣り問題研究会は、2005年06月25日(土)東京海洋大学にて開催された。
「魔魚狩り」の著者で、環境省特定外来生物諮問委員であった、水口憲哉先生の退官記念特別講義ともいうべき内容で、
第1回釣り問題研究会は、2005年06月25日(土)東京海洋大学にて開催された。
「魔魚狩り」の著者で、環境省特定外来生物諮問委員であった、水口憲哉先生の退官記念特別講義ともいうべき内容で、
1「社会現象としての釣り問題」
2「釣り場環境の変遷と釣り」
3「釣魚資源の増減と環境問題との関係」
4「自然への関わり方の多様化」
5「社会、経済情勢の変化」
6「釣りをめぐる制度的な問題」
7「東京湾の釣りの考察」
というテーマが示され、活発な質疑応答があった。
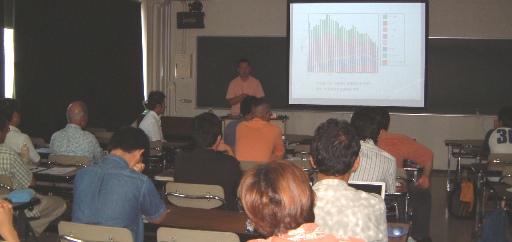 続く第2回釣り問題研究会は、2005年07月23日(土)東京海洋大学にて開催された。
続く第2回釣り問題研究会は、2005年07月23日(土)東京海洋大学にて開催された。
「釣りによる資源利用の現状と諸問題」として、
1「釣りによる資源利用の現状」を
「釣り場と対象種」「資源利用実態」「釣り具市場の動向」の観点から、
2「問題の諸相」を
「内的問題」と「外的問題」から解析し、
3「課題」には
「資源利用に関する問題は釣り場と対象種によって多様である」こと、
「内水面は制度的問題と放流問題」を抱えており、
「海面は漁業との競合問題」を持つこと等の発表が工藤先生からなされた。
余談であるが16:30発生の地震のため、よしさんが品川からJRで四街道駅へ帰着したのは翌日00:40、なんと7時間におよぶ
長時間通学となった。
 さらに第3回釣り問題研究会は、2005年09月17日(土)東京海洋大学にて開催。
さらに第3回釣り問題研究会は、2005年09月17日(土)東京海洋大学にて開催。
「内水面における釣り問題の諸相」として、
1「サケ・マス釣りの現状と問題」を堀内正徳氏(フライの雑誌社)が、
2「アユ釣りの現状と問題」を大久保芳木氏(奥多摩友愛会)が、
3「ヘラブナ釣りの現状と問題」を沢田典大氏(マルキュー株式会社研究開発部)が、
それぞれ発表された。
「サケ・マス釣りの現状と問題」では、マス釣り場管理者と釣り場形態による、多種多様な釣り方・ルールが報告され、
北海道における稚魚の数釣り(ン百尾単位)・マスの泳ぐ河川のコンクリート護岸化・漁協による週末客向け大型魚の数日前放流恒例化(河川の釣堀化)他の
問題点が提起された。
神奈川県世附川(よづくがわ)の事例では、釣り人の知らないところでルールが決まってしまい、議論する場もないと渓流マン一般が抱く
戸惑い・悩みの提示もあり、釣り人の嗜好が多岐にわたる広範な分野の基本部分が良くまとめられた発表であった。
欲をいえば、北国から「サケ釣り」について報告したいという有志の参加がなかったのが惜しまれ、また、レイクトローリングにも触れず仕舞いであったことは残念だ。
 「アユ釣りの現状と問題」については、東京湾のアユを多摩川へ溯上させたいという主旨の「市民団体風」発表に偏向し、
日本を代表する狩野川・球磨川・那珂川等の釣り場や、主力の釣り方である友釣りへの現状認識・問題提起・今後解決すべき課題の
言及がなく、的を外していたため、日刊スポーツ水上氏他の反論が相次いだのも、うなずける。
「アユ釣りの現状と問題」については、東京湾のアユを多摩川へ溯上させたいという主旨の「市民団体風」発表に偏向し、
日本を代表する狩野川・球磨川・那珂川等の釣り場や、主力の釣り方である友釣りへの現状認識・問題提起・今後解決すべき課題の
言及がなく、的を外していたため、日刊スポーツ水上氏他の反論が相次いだのも、うなずける。
釣り問題研究会の発表の場では、正確で豊富な現状認識に基づく、釣り場・釣り方等にまつわる大局的な問題提起がなされるべきである。
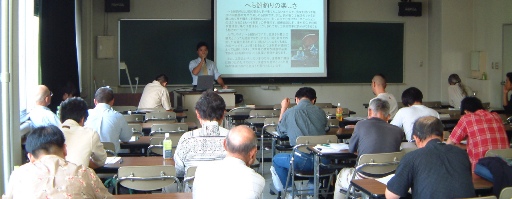 「ヘラブナ釣りの現状と問題」の中で、ヘラブナは全て某ヘラブナ釣り愛好団体が放流してきたとする発表者の認識は誤りであり、
少なくとも亀山湖・笹川湖においては、漁協の費用負担で放流されていることを、ここに明記しておこう。
「ヘラブナ釣りの現状と問題」の中で、ヘラブナは全て某ヘラブナ釣り愛好団体が放流してきたとする発表者の認識は誤りであり、
少なくとも亀山湖・笹川湖においては、漁協の費用負担で放流されていることを、ここに明記しておこう。
問題提起と今後解決すべき課題に関して、
釣り場の水質環境(特に富栄養化)に配慮する「より有機物量の少ない新型エサ」の研究開発や、バスフィッシングの流れを汲み初心者が
ベテランと競いやすい「5尾重量制ルール」導入による新たなゲーム性確立等は評価できることで、よしさんも賛同したい。
発表と質疑を元に進行役の工藤先生がまとめられた、
A「釣り場における、他の釣り物・釣り方との競合の有無、あるいはルールの有無」
B「現状の漁協による釣り場管理・放流事業への評価」
C「今後の釣り場管理・放流事業のあり方について」
は、参加者多数が各々意見を発表し、17:00を過ぎる白熱ぶりであった。
よしさんもAにつき、小櫃川漁業協同組合・亀山湖における、ニジマス・アユ・ヘラブナの場合は、釣り場と釣り方が重複せず競合のないこと、
漁協ルールと自主的ルールにより運営されている事例を報告した。
他方、BとCについては、釣り人が評価を漁協へフィードバックする場と方法論の確立、および
釣り人がリクエストを伝える場と方法論の確立こそが大事ではないかと考えていることを訴えた。
今後それが、全国的にオーソライズされることが望ましいが、当面は小櫃川漁業協同組合・亀山湖ローカル単位でも、
「場と方法論の確立」に微力ながら努力してゆきたい旨、意見提出した。
第3回の参加者も、水産庁桜井釣人専門官をはじめ、
社団法人全日本釣り団体協議会東京都城東の小林氏・日本友釣り連盟高橋氏・日刊スポーツ水上氏・フィッシングライター谷剛氏・FB’s福原毅氏・
裏磐梯アングラープレスの浦伴編集長・学生諸君他と、多彩な顔ぶれだった。
次回、第4回釣り問題研究会は、2005年10月22日(土)「海面における釣り問題の諸相」として、
「岸釣り」「船釣り」「トローリング」の3項目をテーマに、東京海洋大学にて開催予定。
これまた、おもしろい意見が聴けそうで、楽しみである。
諸兄も参加されては、いかが。