[整理番号:0095]
2005年06月01日より、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」が施行される。
魚類に限らず、哺乳類や無脊椎動物、植物も含め、第1陣37種が防除(駆除・殺処分)対象である。
貴重種の在来生物を守るために、運搬・保管・飼養・譲渡・輸入等については一定の法規制がなされる。
ただし、オオクチバス釣りについては、釣りそのものはもちろん、キャッチ&リリースも禁止されない。
だからほぼ従来どおり、釣りをすれば良い。
ほぼというのは、釣り大会の検量場面等に若干の注意が必要となるからだ。
その注意事項については、すでに別項でまとめ、発表したものを参考にして頂きたい。
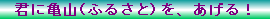 ☆
☆
普通はここまでであろうけれど、もう一歩、法の主旨に寄り、
この機会にオオクチバス釣り人も、オオクチバスの有効利用を生業とする人々も共に、新しい秩序の創造と実施を
はかることを、よしさんは提唱する。
☆
釣り人には、新しい価値観の構築を求めたい。
数を追うよりも、1尾の釣果を誇りたい。
例えば釣り大会規定もキーパーサイズ制限なしを30cm以上に・キープの3~5尾は1尾のみへ・
成績も1尾重量というように。
他方、オオクチバスの有効利用を生業とする人々にも、さらなる努力を求めたい。
オオクチバスが漁業権魚種になっていなくても、現に生息しているのだから、拡散源とならない方策を
すみやかに講ずるべきである。
例えば生体持ち出し禁止看板設置・生業者地域住民釣り人有志による監視体制整備・市条例制定運動促進というように。
法の第2陣指定候補のセイタカアワダチソウやブタクサのように、有効利用の道もなく、万人に嫌われている種とは違い、オオクチバス
によって経済的メリットを得ている人々に、新たな秩序の形成が求められているものと、法に義務規定がなくても深慮したい。
☆
ついで、よしさんの考え方をまとめれば、次のようになる。
①漁業権魚種になっていない水域では、生業のため新たな秩序の下に、自主的な利用管理をしてゆく
②希少種生物の保全が必要な小水域では、できるだけ(※1)防除してゆく
③新しい水域への拡散は、できるだけ(※2)防止してゆく
(※1)希少種生物に悪影響を与えない防除方法に限定されるため。
(※2)直接人為的な拡散には厳罰があるが、導水路網等による間接人為的拡散をも防止したい。
世界が人跡未踏の原生自然であってこそ、人間は最高の幸せがつかめる、とは到底思えない。
自然の保護と保全は別の思想であり、人間の幸せのために自然はある程度利用されて良いと、よしさんは信じている。