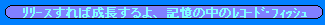さて、今回は正月の、オトシダマです(前編は、バックナンバ−をご覧下さい)。
イは、どうか。
舟を流してゆくと、“オッ!”と思うような絶好のポイントが、見えて来る。そこは
毎日(そして日に何度も)釣り人が、入れ替わりキャストしている場所である。
平均サイズならいざ知らず、超大物がそんな所にいるはずもない。
つまり、釣り人は無意識の内に「見える所に、変化がある」ことを基準として、
ポイントを選択していたのだ。
このことは、水面上の風景なり、水面下のブレイクなり、スタンプなりがキャスト
するか否かの、判断基準であることを指している。
そこで、前回の釣行を振り返って見れば、“オッ!”と思った所でノ−ヒットだった
場合、10人中、10人が舟をスタ−トさせ、次なる“オッ!”の場所まで移動して
行くではないか。
これでは、移動途中の何の変化もない(と見えるだけで、本当は大変化がある
かも知れぬ)場所にBIG FISHがいたら、手中にするチャンスは消えてしまう
ことになる。
小物や平均サイズの、数釣りで楽しむのではなく、記録物を得たいと希望
するのであれば、「その釣行日は丸一日掛けてでも、いかにもつまらなそうな、
何の変哲もなさそうな場所にのみ、キャストを続けて行くこと」が、
ひとつの結論として浮上する。
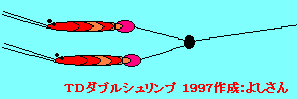
ロは、どうか。
同じく舟を移動させて行くと、ゴミ・流木の吹きだまりが見えて来る。
良いポイントだと思うが、アプロ−チの一番手前の水面に流木・竹が横たわって
いる。
一番奥に水面が一部見えているが、キャストは出来ても、
手前の障害物のため、魚の取込みは無理のようだ。
そんな場面は、誰にもある。
そこで、手前の吹きだまりのエッジ部分に数回のキャストを試みる釣り人が少々。
大多数は「一目見て、パス」してしまう。
この場合も、奥の壁際の水面下にBIG FISHがいたら、・・・。
何と言っても、ルア−がキャストされない(もしくは、年間に数回以下しか
ルア−が飛び込まない)のだから大物は安全である。
この例以外にも、「10人中、10人がパスしようと考える場所」はある。
「一目見て、ストラクチャ−は絶好だが、とても手が出せないと思う所こそ、
攻める価値がある」という、二つ目の結論が得られる。
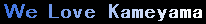
「BASSはどこにいるのか」のまとめ。
(人に対して)安全な所であり
それは、釣り人に発見されない所
または、釣り人がキャストしない所
である。
以上から、釣り人に対して安全だと記録魚が考えている場所、
つまり居場所が、解る。
他に、「餌の捕食が容易で」
「生息環境の良い所(DO,水温,日蔭,カバ−)」
との要素があることは、前に述べた。
確度の高い表現で別の言い方をすれば、
「記録魚は本能的に居場所を決するようだ」と言ってもよい。
いかがでしたか。エッ!
居場所は、わかった。
どうして、どのような方法で釣るのかって?
ウ〜ン。おいおい発表させて頂きますか。