採取した水生植物の全景を最上段に示す(fig.01)。
採取部分の茎は円柱形で径1mm、節の間隔は最大7mmから5mmで、先端の間隔はさらに詰まっている(fig.02)。
茎の節(不定)から白色糸状の根を出すが、一つの節から根は1本のようだ(fig.03)。
根の太さは元で0.6mm、先端は0.4〜0.2mm程になり、最先端は鈍頭(fig.04-fig.05)。
節に葉が輪生し、節(不定)から枝も分岐させる(fig.03)。
輪生葉は、元側の節で2枚、その先の節で3枚、葉片は暗緑褐色、無柄で線形軟質、葉縁に細鋸歯がある(fig.01,fig.08)。
葉片の長さは9、10、12mm、幅は1.0mm、中央脈が明瞭である(fig.09)。
採取した水生植物は、採取地環境(後述)と観察結果から、『日本水生植物図鑑』(※01)・他により、北米原産で
植物生理の実験用として移入した沈水性多年草の一種、トチカガミ科のコカナダモ Elodea Nuttalli (Planch.) St.John と同定した。
【考察】
『日本の生物』(※03)に、「図2 コカナダモの分布」の日本地図が掲載されており、ちょうど千葉県の雄蛇ケ池付近に
白丸印が付され、標本でなく、文献上で分布を確認したとされている(57pp)。
著者は角野康郎博士であるが、白丸印該当文献は、千葉県出身の國井秀伸博士の業績であろう。
『日本の生物』(※04)に、コカナダモが分布を広げ定着するメカニズムについて、國井秀伸博士は
「コカナダモの切れ藻は、照度が高いと沈降し、照度が低いと浮上することを、繰り返して生活している」と、
述べている。
コカナダモの切れ藻が、上記の垂直移動と、風・波浪・対流・流下等による水平移動を、種族繁栄の戦略として駆使
することは驚異的であるし、その解明もまた大変独創的な仕事である。
國井秀伸博士は、雄蛇ケ池の水生植物が減少すれば、日射が底まで届きやすくなり、結果として水温上昇を招くとの指摘も、
早くからされている(※02)。

fig.10 農業用水路全景 (撮影 20110717)

fig.11 コカナダモの繁茂状況 (撮影 20110717)

fig.12 RC造巨大U字溝に改変された (撮影 20110717)
採取した農業用水路は、西岸が矢板・東岸が鋼矢板で垂直護岸となり、底は砂泥質、水深は10cm程度と浅いものの常時流速がある(fig.10-11)。
永らく(特に夏季は)その環境下で、コカナダモは繁茂していたが、圃場整備事業の一環としてか、
採取日現在ボートハウス ツカモト隣接区間は、コンクリート製巨大U字溝の活け込みに改変された(fig.12)。
同区間の上下流も、早暁同様構造になる可能性があり、農業用水路に生息するコカナダモ以外の水生植物、及び
魚介類は大きな打撃を受けることが予測される。
水田稲作減反(用水量減少)の昨今、加えて、三面コンクリート張り水路が、生態系に悪影響を及ぼす多くの事例が
示されて久しい当節、水路の構造改変はいかがなものか。
外来種コカナダモと在来種クロモの区別は間違えやすいとされるが、クロモは別途報告している(※07)。
コカナダモと同日に観察した、雄蛇ケ池のプランクトン・ヒメネコゼミジンコ・フクロワムシ・藍藻類については、別途報告した(※08〜※11)。
雄蛇ケ池のイチョウウキゴケについては、以前報告している(※06)。
【参考文献】
(※01)大滝末男・石戸 忠(1980):「コカナダモ」.『日本水生植物図鑑』.北隆館,東京,190-191pp.
(※02)Hidenobu KuNiI(1984):Seasonal Changes in Water Quality and Surface Cover of Aquatic Plants in Pond Ojaga-ike, Chiba, 1978-1980.
Memoirs of The Faculty of Science, Shimane University, 18, pp.59-68,
暫定和訳:国井秀伸(1984):1978年から1980年における千葉県雄蛇ケ池の水質と植被の季節変化.島根大学理学部紀要(18)67pp
(※03)角野康郎(1989):日本の水草 その自然史9「帰化水草の生態」.『日本の生物』3(4),APR,1989,56-57pp.
(※04)角野康郎(1989):日本の水草 「座談会水草を語る」.『日本の生物』3(7),JUL,1989,62-63pp.
(※05)よしさん(1996〜2010):雄蛇ケ池「ザ・レイクチャンプ」http://lake-champ.com
(※06)よしさん(2008):「千葉県雄蛇ケ池におけるイチョウウキゴケ現存量」http://lake-champ.com/odl0118.htm
(※07)よしさん(2010):「群馬県榛名湖のクロモ」http://wakasagi.jpn.org/
(※08)よしさん(2010):「師走の雄蛇ケ池における魚類餌料プランクトン調査報告(2010)」http://wakasagi.jpn.org/
(※09)よしさん(2010):「千葉県雄蛇ケ池のヒメネコゼミジンコ(続報)」http://wakasagi.jpn.org/
(※10)よしさん(2010):「千葉県雄蛇ケ池のフクロワムシが捕食したもの」http://wakasagi.jpn.org/
(※11)よしさん(2010):「師走の雄蛇ケ池における藍藻類観察報告」http://wakasagi.jpn.org/
|
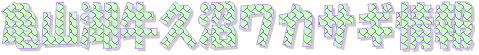
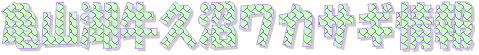

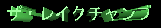 Copyright by yoshisan.
Copyright by yoshisan.