
|
|
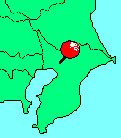
|
| 0009 |
|
| 新川(しんかわ)Shinkawa River. |
|---|---|
|
| 千葉県印旛郡印旛村、印西市、佐倉市、八千代市、 |
|
| 河川(排水路) |
|
| 印旛疏水路、印旛新川、印旛沼放水路、(花見川) |
|
| 京成電鉄本線京成臼井駅より、北へ約2km(上流部)。 |
| 京成電鉄本線勝田台駅より、西へ約1km(下流部)。 | |
| 上流部へは、国道296号線(成田街道)を東進し佐倉市に入る。 | |
| 中宿信号(T字路)を左折。 | |
| 県道千葉・臼井・印西線を北上し、船戸大橋を渡って、すぐ | |
| (左ト/信号なし)左折。左手一帯。 | |
| 下流部へは、国道296号線(成田街道)を東進し、国道16号線と | |
| 立体交差の下市場信号を、左折。 | |
| 国道16号線に合流して北上、300m先(Y字路)を左へ入り、 | |
| 直進。 | |
| 信号(左ト)を左折すれば、村上橋である。 | |
|
| ・・・ |
|
| 4m |
|
| 不詳 |
|
| 現状は、1969(昭和44)年03月31日。 |
|
生息確認年月 | 1985(昭和60)年09月14日。 |
|
| 上流部は、船戸大橋南詰めに、ふな一ボート(電話043-461-6204・ |
| トイレあり)と、朝比奈ボート(電話043-489-5301・木曜定休 | |
| ・祝日は営業)がある。下流部は、貸しボート店なし。 |

|
| 印旛沼西部に続く船戸大橋から、阿宗橋迄の3.5kmは、平均川幅 |
| 約180m程。蒲・葦・矢板・インレット・グレ・橋脚等のストラクチャーがある。 | |
| 阿宗橋から、大和田排水機場迄の8.5kmは、平均川幅60~80m程。 | |
| 両岸共、土手を歩いて探れるのが嬉しい(車両は不可)。 | |
| 橋脚・水門・インレット・護岸の変化・杭・カケアガリ等の狙い所が豊富。 | |
| けれど、BASSの固体数は、激減している。 | |
| 主な原因は水質にあるようで、新川の支流桑納川は印旛沼水系で最悪の | |
| 水質(BOD10mg/l以上・リン153kg/日)だ。 | |
| 桑納川の上流部の習志野台団地・高根台団地等から、家庭雑排水が流入 | |
| しており、村上橋付近に八千代市が、ばっ気装置を設置し水質浄化に努めて | |
| いるが、効果は焼け石に水といった程度が実状だ。 | |
| 台所・風呂・洗濯・洗車等の雑排水をU字溝に流すのは、新川と印旛沼の | |
| 魚を殺すことに直結する。 | |
| 公共下水道のないエリアでは、石鹸の使用(合成洗剤・シャンプーの不買 | |
| ・不使用)・使用済油の固化処理(可燃物ゴミ可)を推奨する。 |

| 新川に鯉・真鮒・タナゴ・ヘラブナ・モロコ・レンギョ・ブルーギル・ヨシノボリ・ | |
| ドジョウ・ザリガニ・ミドリガメ等が生息。八千代市も錦鯉を放流している。 | |
| ヘラブナは、毎年のように放流されることもあって、安定した個体数と | |
| 推定される。 | |
| 48時間運転で、印旛沼の水を全て排水する能力を持つ、大和田排水 | |
| 機場の南から、千葉市花見川区を経て、同美浜区の美浜大橋から | |
| 東京湾へ注ぐ区間は、花見川と呼ばれる。 |
|
| 弁天橋付近から、柏井橋付近は分水界を開削した所で、江戸幕府が何度 |
| も挑みながら成功しなかった場所である。1883(明治16)年の大日本帝 | |
| 国参謀本部陸軍部測量局の迅速測量図を見ても、印旛沼側の勝田川と | |
| 東京湾側は、繋がっていない。 | |
| 新川は、元来勝田川であり、勝田川は支流の桑納川・神崎川の水を | |
| 併せて、印旛沼へと流下していたのだ。 | |
| 現在の姿になったのは1948(昭和23)年より、総事業費177億円・干拓 | |
| 面積1397ha・土地改良6559ha・工業用水取水6.8m3/秒の、印旛沼開発 | |
| 事業の完成した1969(昭和44)年03月31日である。 | |
| 印旛沼の水害を防止するため、花見川との間に新しく開削された排水路 | |
| なので、その名も新川と言われている。 |

|
|
| また花見川は、検見川村を流れる川で、古くは気見川とも別記された。
| ケミは毛見であり検見と同意。
| 武家時代、稲の穂がでるころ領主が役人に稲作のでき具合を検分させ、
| 年貢を定めたことから、との説がある。
| 村上橋東詰めから500mのところに、八千代市歴史民俗資料館
| (電話 0474-84-9011/月曜・祝日・年末年始休館)が、1993(平成05)年
| 05月開館。
| 「新川流域の自然と人々のかかわりの変遷」を常設テーマとしている。
| 村上橋西詰めから300mの、八千代市民会館には、国際的な木版画家・
| 星襄一(ほしじょういち)版画展示室(電話0474-83-5111/火曜・年末年
| 始休館)が、1988(昭和63)年開設され、代表作「樹」シリーズが展示されて
| いる。
| 八千代市大和田新田には愛好家垂涎の、京成バラ園芸八千代農場
| 電話0474-59-3347/火曜・年末年始・お盆休館)がある。
| バラの見頃は5~6月と、9~11月。
| 印旛村岩戸には、印旛村歴史民俗資料館(電話0476-99-0002/月曜・
| 祝日・年末年始休館)があって、印旛沼漁労関係を展示する。
| 佐倉城跡には、おなじみの国立歴史民俗博物館(電話043-486-0123/
| 月曜・年末年始休館)があり好みに応じ、訪ねるのも楽しかろう。
| |

|
| 昭和初期の、白井・神崎川・神崎橋(印旛沼の落し)や、大和田・寺台一帯の |
| タナゴ釣りは、益田 甫が『河川の釣』に描いている。 | |
| 昭和30年代の、神崎川・神崎橋の上下一帯のタナゴ釣りについては、 | |
| 大橋青湖が『釣の風景』「タナゴの釣場・神崎上流の釣場」(45PP)に | |
| 紹介している。 | |
| 印旛村周辺に伝わる郷土料理に、鮒のたたき汁がある。 | |
| 晩秋から春先にかけての料理として古くから作られ、祝いごとや、村の | |
| 行事等にかかさず作られている。その、五人分の作り方。 | |
| 鮒五百gは頭、尾、こけら(ウロコ)、内蔵とそのまわりの黒い膜を取り除き、 | |
| よく洗い、ざるにあげる。鮒(正味三百g位)をひき肉機に通し、すり鉢 | |
| でよくする。ひき肉機のない場合は出刃包丁でよくたたいてから、すりお | |
| ろす。その中に味噌百五十g(つくり味噌ですり身の量のおよそ | |
| 半分位)をすり混ぜ、さらに卵二ケを入れてよく摺る。 | |
| 鍋に湯(約1.5リットル)を煮たたせ、うす切りの大根(三百g)を入れ、 | |
| 沸騰させる。 | |
| その中に鮒のすり身を小さくちぎって落とし(材料を木杓子に乗せ、小指 | |
| の先位の大きさに箸でちぎって落とす)味噌の塩味が中から出て、 | |
| 汁に味がついたら、火を止める。 | |
| 椀に盛り、柚子(ゆず)の皮のせん切りを添えて、すい口とし、熱いうちに | |
| いただく。 | |
| 作ってすぐも美味しいけれど、暖め直しても美味しく食べられる。 | |
| コツは、鍋の蓋を開けて煮ることで、冬場に挑戦したい料理だ。 | |
| 印旛郡印旛村に、牛むぐり池(牛潜池/萩原・瀬戸)がある。 | |
| 釣り人が、率先・師範して、生きた川を取り戻したいものだ。 |
| 〇河川の釣 益田 甫 現代日本の釣叢書 | 1941(昭和16)年11月20日 | |
| 水産社 | ||
| ○『釣の風景』大橋青湖 | 1958(昭和33)年09月10日 | |
| スポーツ新書82 ベースボール・マガジン社 | ||
| ○印旛沼開発史第一部(上下) | 1972(昭和47)年03月20日 | |
| 栗原東洋 印旛沼開発史刊行会 | ||
| ○印旛沼開発史第二部 | 1976(昭和51)年07月20日 | |
| 栗原東洋 印旛沼開発史刊行会 | ||
| ○日本全河川ルーツ大辞典 | 1979(昭和54)年05月15日初版 | |
| 竹書房 | ||
| ○印旛沼開発史第三部 | 1980(昭和55)年05月30日初版 | |
| 栗原東洋 印旛沼開発史刊行会 | ||
| ○房総のふるさと料理 | 1982(昭和57)年01月2刷 | |
| 千葉県農業改良協会 | ||
| ○月刊へら専科 印旛新川徹底研究Ⅰ | 1985(昭和60)年11月01日 | |
| 投稿記事 池田正躬 三和出版 | ||
| ○月刊へら専科 印旛新川徹底研究Ⅱ | 1985(昭和60)年12月01日 | |
| 投稿記事 池田正躬 三和出版 | ||
| ○日本のへら鮒釣り場写真集 | 1985(昭和60)年12月15日 | |
| 日本へら鮒釣研究会 編発行 | ||
| ○月刊 TACKLE BOX No.49 | 1986(昭和61)年03月 | |
| 投稿記事 島田圭一郎 フリーウェイ | ||
| ○行こうさぐろう緑と水辺 | 1988(昭和63)年03月31日第1刷 | |
| 千葉市自然研究会 千葉市 | ||
| ○ちばの博物館 | 1994(平成06)年03月15日 | |
| 千葉県博物館協会 | ||
| ○東金街道史跡散歩 本保弘文 | 2000(平成12)年12月20日 | |
| 暁印書館 |
 Copyright by yoshisan.
Copyright by yoshisan.