
|
|
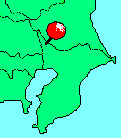
|
| 0008 |
|
| 大沼(おおぬま)Oonuma swanp |
|---|---|
|
| 千葉県東葛飾郡関宿町木間ケ瀬 |
|
| 池(旧河川の一部) |
|
| |
|
| 東武鉄道野田線川間駅より、北東へ約5km。 |
| 埼玉県からは国道16号を東進し、江戸川を金野井大橋で渡り | |
| 千葉県野田市へ入る。“中里”陸橋を越え、川間小学校前の | |
| 歩道橋を過ぎたら200m先の信号を左折東進。 | |
| 【柏方面からは、国道16号線を北上し、“船形南”信号の先1.8km | |
| の信号(川間小学校の歩道橋より200m手前)を右折】を道なりに、 | |
| 利根川堤防迄約2.8km直進。 | |
| 利根川堤防(T字路)を左折北西に進む。 | |
| 1.1km程(機場の)先を左折西進。400mである。 | |
|
| 23.800m2 |
|
| 2m |
|
| … |
|
| 元和年間(1615-1623)以降 |
|
生息確認年月 | 1995(平成07)年09月23日 |
|
| 貸しボートなし・トイレ・売店なし |

|
| 東西140m・南北170mの、本当の小場所。 |
| 専門に狙う程の場所ではない。大沼への正しいアプローチは | |
| 利根川・江戸川等の新規開拓と組み合わせた、車でのラン&ガン | |
| であろう。 | |
| 沼を冠しているが、現状は池である。 | |
| 周囲は水田地帯で、東岸は南北に利根川(流路延長322km、 | |
| 流域面積16.840km2)の堤防に抱かれる。 | |
| 西岸は道路であり、一部は堰堤がコンクリート製で足場は良い。 | |
| 他は土壌である。辺地には、直径15~20cm程度の木の幹が | |
| 沈めてあり、ストラクチャーとなっている。 |

| 水色はマッディー。水面は、オープンである。 | |
| ブルーギル・マブナ・ヘラブナ・鯉も生息。 | |
| ジグヘッド+グラブの練習には、好適と見た。 | |
| 南岸中央に、流出口がある。 | |
| 流末は、南流し野田市で、安部沼落しと合流し、関宿落掘りに入り、 | |
| 東葛北部土地改良区排水機場と川間排水樋管により、利根川に | |
| 排出される。 | |
| 大沼の北(上流)に別の小池があり、そこにもBASSがいるらしい。 |
|
| 1883(明治16)年の大日本帝国参謀本部陸軍部測量局の迅速 |
| 測量図「岩井村」にも、大沼が見えている。 | |
| 当時も今も沼そのものは、変わっていない。 | |
| ズバリ、ここは太古の利根川なのだ。 | |
| 関宿といえば、利根川と江戸川(流路延長53.2km、流域面積…km2) | |
| が分流する所である。しかし、1590(天正18)年以前は利根川 | |
| (加須・川口・春日部・千住へと注いでいた)・渡良瀬川(栗橋・金杉・ | |
| 野田・千住へ注いでいた)?常陸川(関宿以東の現在の利根川)の | |
| 諸河川が乱流していた。 |

| 利根川が現在の姿になった経緯のさわり部分だけを、紹介しましょう。 | |
| 小田原城の北条氏直を破った豊臣秀吉は、殊勲の徳川家康に | |
| 1590(天正18)年07月、関八州を与えるとの内示をだした。 | |
| 家康の側近の多くは、未開の原野だった関東平野の領有に反対 | |
| したが、勘定奉行伊奈備前守忠次は、江戸が江戸湾に臨み、 | |
| 背後に関東平野が控え、将来の発展性を強調、領有を進言した。 | |
| 1590(天正18)年08月、家康は忠次の言を入れ、江戸入城。 | |
| 忠次を関東郡代に任じ、利根川の東移計画立案と工事を命じた。 | |
| 1594(文緑03)年着工から、1654(承応03)年赤堀川の増削 | |
| (川幅10間を13間に広げ、同時に河床を掘り下げた)まで、 | |
| 忠次・忠治・忠勝(忠克)と3代に亘り、60年の歳月を費やして、 | |
| 17世紀の世界的大土木工事といわれた、利根川東移の治水事業は | |
| 完成された。 | |
| 木間ケ瀬村堤根から(大沼を経て)川間村船形に南偏し、(関宿 | |
| 落掘を経て)茨城県岩井市筵打(むしろうち)に続く、元和年間 | |
| (1615-1623)以前の常陸川(現在の利根川)流路は、元和年間の | |
| 洪水により、木間ケ瀬村堤根から中川村小山を経て筵打に至る | |
| 流路になったと云う。 | |
| 伊奈郡代忠治(通称半十郎、本姓源伊奈忠次の子)は、福岡堰 | |
| 等にも治水の手腕を発揮している。 | |
| 詳細に興味のある方は「利根の変遷と江戸の歴史地理/吉田東伍」・ | |
| 「利根治水論考/吉田東伍」・「利根川治水史/栗原良輔」・「中利根 | |
| 川の治水史/川名晴雄」等を参照下さい。 |

| 釣り人のために、「関宿志」に記された[関宿閘門の馬鹿つり]を | |
| 紹介しよう。 | |
| 水門の上から、長い長い釣り糸に、急流に流されないよう大変に | |
| 重い錘と、餌も何もつけない釣り針4~5ケ付けて河中に投げ込み、 | |
| 釣り竿を上げ下げしていると、産卵のため群れをなして下流より | |
| 上がってくる魚(マルタが多い)が、半開きになった水門に阻まれて | |
| 上がることも出来ず、水門の下流の渦を巻いて流れる川の中を、 | |
| ぐるぐる泳ぎ回っているうちに、自分から馬鹿釣りの釣り針に | |
| 掛かってしまう。 | |
| 馬鹿な魚を釣り上げるので、馬鹿釣りだと呼んで、東京辺から | |
| 来た釣り人で賑わったものである。 | |
| 今では、水門も全開されていて、マルタもすいすい上がってしまうから | |
| 名物の馬鹿釣り風景は見られなくなった。 | |
| [関宿閘門の馬鹿釣り]は、ルアー釣りとは似て非なるもの。 | |
| あえてこじつければ、ボラのギャング釣り・アユのコロガシ釣りと | |
| 同様、魚が口で食いつくのではなく、掛け鈎で魚体を引っ掛ける | |
| 釣り。そこは魚の意志(餌への)が介在しない、異次元の世界。 | |
| 似た釣法でハヤ(石班魚・ウグイ・マルタ)の転引釣(ゴロビキ)や、 | |
| 吹飛釣(フットバシ)については、村上静人が『ヒガヒ・石班魚釣秘伝』 | |
| に記している(152pp.157pp)。 | |
| 森田春雄は『関東百万人の鮒釣場案内』で、関宿の悪水落し・ | |
| 阿部沼落し・郷の沼他の、フナ・ナマズ釣りを紹介している。 | |
| ご当地・木間ケ瀬落しや、利根川対岸の菅生沼(別項参照)・ | |
| 初崎池等の、戦前のヘラブナ・マブナ釣り場の案内書に、 | |
| 加納幸蔵の『鮒の釣場』がある。 | |
| 野田市に、五駄沼・八間掘・白鷺の池(下三ケ尾/しもさんがお)等がある。 | |
| 関宿町に、関宿博物館(新田戸)があり、1995(平成07)年11月11日 | |
| には、千葉県立関宿城博物館(電話0471-96-1400/月曜・年末 | |
| 年始休館)が、10館目の県立博物館として開館している。 |

| [参考文献] | ||
| ○ヒガヒ・石班魚釣秘伝 村上静人 | 1932(昭和07)年11月10日 | |
| 奎文社 | ||
| ○関東百万人の鮒釣場案内 森田春雄 | 1941(昭和16)年12月20日 | |
| 三弘社 | ||
| ○鮒の釣場 加納幸蔵 | 1944(昭和19)年01月18日 | |
| 春陽堂書店 | ||
| ○利根川 飯島博 | 1958(昭和33)年03月15日第2版 | |
| 三一書房 | ||
| ○千葉県統計年鑑(昭和42) | 1968(昭和43)年03月25日 | |
| 千葉県企画部統計課 | ||
| ○関宿志 奥原謹爾 | 1973(昭和48)年03月01日 | |
| 関宿町/関宿町教育委員会 |
 Copyright by yoshisan.
Copyright by yoshisan.